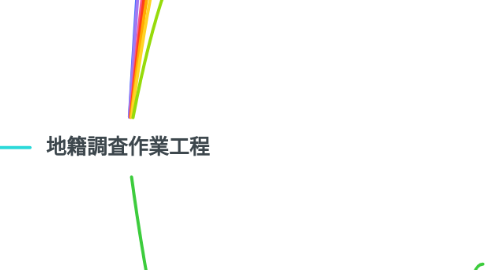
1. 安全管理の徹底
1.1. 手袋、ヘルメット
1.2. ハチ、アブ、蚊対策
1.3. 熱中症対策
1.4. 熱は無いか
1.5. 最寄りの病院確認
2. 地理院成果の入手
2.1. 測量協会へ成果謄本等交付申請
3. 地籍調査地区(単位区域界)の不突合について、法務局との協議が行われているか。 地籍調査地区(単位区域界)の中に造林公社が管理する造林地がある場合「地上権設定含む」立入は適切か。 地籍調査地区(単位区域界)の中に保安林がある場合、 事前現地調査の実施について十分な調整は図ったか。 地籍調査地区(単位区域界)の隣接把握は行ったか(過年度地籍調査、同時進行中地籍調査、国有林、土地改良事業など)。 地籍調査地区(単位区域界)の隣接において土地所有者の現地立会(確認)は必要か。 社内の地籍管理システム「マルコポーロ」の使用にあたり、発注者に承諾を得たか。使用する場合、調査地区及び隣接地区のデータ有無を確認したか(登記異動処理が発生する場合はどの時点のデータを使用か確認が必要)。 積算上は計上されていないが、復元測量の必要はないか。 図面等調査について発注者の考え(方針)を確認したか。 筆界表示杭の設置は受託者で良いか確認したか。 調査時の課題・問題は、どのようなタイミングで報告するか。 必要な資料提供(法務局地図XML等)の申し出は行ったか。 外字の扱いについての確認は行ったか。所有者コード・共有者代表コードの使用・不使用の扱いについて確認は行ったか。 ☆調査時または調査後の確認 調査の問題点(今後の課題)について整理し、法務局協議を発注者に依頼したか。また、回答は得ているか。 所在不明所有者等の認証請求書類の作成は行ったか。 登記所との協議実施書が必要な場合あり。 地方公共団体による筆界特定制度の活用はあるか。
4. 初回打ち合わせ
4.1. 業務計画書(案)の提出
4.2. 調査範囲、筆数の確認
4.3. 身分証明書発行の届け提出
4.4. 現地立ち入り時期についての協議
4.5. 地元説明会の有無
4.5.1. 推進委員会の開催時期
4.5.1.1. 一筆地調査開始時期
4.6. 法務局調査について
4.6.1. 初回挨拶の同行日時
4.6.2. 公用閲覧申請依頼書の発行願い
4.7. 過年度必要資料の貸与
4.7.1. 既設基準点データ
4.7.2. 関係機関の図面等
4.7.3. 調査済み区域の成果
4.7.3.1. 地籍フォーマット2000
4.7.3.2. SIMAデータ
5. 基準点使用申請書の提出
5.1. 使用承認申請書
5.1.1. https://www.gsi.go.jp/LAW/2930-30zyou.html
5.2. 業務位置図
5.3. 使用基準点附図
6. QGISプロジェクト
6.1. 各工程よりデータを収集し作業しやすいプロジェクトを構築する
6.2. G空間情報センター
6.2.1. https://front.geospatial.jp/
6.2.1.1. 基盤地図や微地形図、法務省XMLなどがダウンロード可能
6.3. 地図タイル収集
6.3.1. https://note.sngklab.jp/?p=627
6.3.1.1. 地理院ほか
7. E工程
7.1. 事務支援現場作成
7.1.1. データ取り込み
7.1.1.1. 属性CSV取り込み
7.1.1.1.1. 字コード
7.1.1.1.2. 権利コード
7.1.1.1.3. 所有者コード
7.1.1.1.4. 登記属性CSV
7.1.1.2. 地図XMLデータ取り込み
7.1.2. 接合図作成
7.1.2.1. 一覧図作成
7.1.3. 調査図素図(字図)作成
7.1.4. 現地調査票作成
7.1.4.1. 原因異動入力
7.1.4.1.1. 30条関係の整理
7.2. 地積測量図の仕分け
7.2.1. 地積測量図一覧表の作成
7.2.2. 必要な測量図の抽出
7.2.2.1. 三斜測量図の接合
7.2.2.2. 座標有りの測量図はデータ化
7.2.2.2.1. SIMA
7.2.2.2.2. シェープ
7.3. 現地調査前確認
7.3.1. 国有林が隣接にないか
7.3.1.1. 一部保安林はないか
7.3.1.1.1. 市町村界は事前に調査したか
8. 法務局調査
8.1. 公図の取得
8.1.1. 電子データ XML
8.2. 要約書の取得
8.2.1. 電子データ属性 CSV
8.2.1.1. エラー地番の再取得
8.2.1.1.1. 不突合調書作成
8.3. 地積測量図の取得
8.3.1. 電子データ TIF
9. 測量工程
9.1. C工程
9.1.1. 選点
9.1.1.1. 選点図作成
9.1.1.1.1. 机上で新点の設置個所を選定
9.1.1.1.2. 必要設置数の確認
9.1.1.2. 平均図作成
9.1.1.2.1. 実施者承諾もらう
9.1.1.3. 基準点設置個所の現地踏査
9.1.1.3.1. 上空視界が十分か
9.1.1.3.2. 後続の作業に支障がないか
9.1.1.3.3. 設置個所は基準点の亡失の恐れはないか
9.1.1.4. 基準点設置申請
9.1.1.4.1. 選点図
9.1.1.4.2. 設置筆の要約書
9.1.1.4.3. 設置予定位置を公図に載せた図面
9.1.1.4.4. 設置写真
9.1.1.4.5. 埋設図
9.1.1.4.6. 建標承諾書
9.1.1.4.7. 伐採申請
9.1.2. 設置
9.1.2.1. 設置立会依頼
9.1.2.2. 設置道具・作業工程の確認
9.1.3. 観測及び測定
9.1.3.1. 観測計画
9.1.3.1.1. 観測にかかる人員、日数、機器の調整
9.1.3.2. 観測図
9.1.3.2.1. 適切なセッション計画
9.1.3.3. 観測記録簿
9.1.3.3.1. アンテナ高の測定は水平器を上下
9.1.4. 計算
9.1.4.1. PCV補正は適切なデータを使用
9.1.5. 点検測量
9.1.5.1. 点検箇所の選定10%
9.1.5.1.1. 点検辺数量確認
9.1.5.2. 工程管理者と日程調整
9.1.6. 取りまとめ
9.1.6.1. チェックリスト確認
9.2. FⅠ工程
9.2.1. 選点
9.2.1.1. 机上で選点計画をたてる
9.2.1.1.1. 配点密度
9.2.1.2. 路線名、交点名は何を使用すればいいか
9.2.2. 平均図作成
9.2.2.1. 外角、夾角、2点間距離、路線長、路線の点数は規程内か
9.2.3. 標識の設置
9.2.3.1. 200m又は交点等に本点設置(必携2024P127,152)
9.2.3.1.1. 設置状況写真撮影
9.2.3.2. 多角、放射、開放による新点数の5%以上の現地点検、工程管理者と写真撮影
9.2.3.2.1. 工程管理及び検査の手引きP89
9.2.3.3. 細部放射点(TP)を安易に出さない、視通がとれるなら多角に組み込む
9.2.3.3.1. 細部放射点(TP)を出した場合、打合せ記録簿提出(西谷ルール)
9.2.4. 観測及び測定
9.2.4.1. 観測図
9.2.5. 計算
9.2.5.1. ジオイドモデルは適切か
9.2.5.1.1. 日付の確認
9.2.6. 点検測量
9.2.6.1. 多角法2%以上の点検
9.2.6.1.1. 内30%の立会点検
9.2.6.2. 放射法100%
9.2.6.2.1. 内30%の立会点検
9.2.7. 取りまとめ
9.2.7.1. チェックリスト確認
9.3. FⅡ-1工程
9.3.1. 観測及び測定
9.3.2. 計算
9.3.2.1. 日付の確認
9.3.3. 筆界点の点検
9.3.3.1. 2%
9.3.4. 現地辺長点検
9.3.5. 取りまとめ
9.3.5.1. 復元測量による座標変換座標が有ればそちらを使用
9.3.5.2. チェックリスト確認
